『ヒルビリー・エレジー』、『教養としての金利』、『正しい家計管理』
いくつか本を読んだので感想を書いておく。
ヒルビリー・エレジー(J・D・ヴァンス著)

J・D・ヴァンスというアメリカ人が自分の生い立ちについて語った回想記。彼の故郷がアメリカの「ラストベルト」だったことが話題となり「アメリカの実情をかたる本」としてベストセラーとなった。その後は彼は上院議員になり、今やアメリカ合衆国の副大統領となった。
彼は高校を卒業し海兵隊に行き、州立大学を卒業後にイェール大学のロースクールを修了している。その後、ベンチャーキャピタルの経営やいくつかの企業で働いたあと、上院議員になっている。そして、若干 40 歳でアメリカ合衆国の副大統領、という王道のエリートコースを歩んでいる。
しかし、彼が育ったのはアメリカ貧困地域であり、ドラッグが蔓延していて多くの若者は高校も卒業しないような地域だった。彼自身も母親が薬物中毒者であり、幼少期と青年期に経験したさまざまな困難が描かれている。また、その地域特有の気質、アパラチア的な価値観や経済的な問題が生々しく描写されている。
おととしくらいにどこかで書評を読んでちょっと気になるなーと思っていた。昨年の夏に「へー、この人副大統領候補になったんだ」と思ったら、結局そのまま正式な副大統領になっていた。まだ 40 歳でいつか大統領になってもおかしくないなと思っていて、近年は死語になりつつある「アメリカンドリーム」だなぁと感じた。
本自体は読みやすくてスラスラ読めたし、アメリカ中西部の「ラストベルト」地域にのしかかる社会の重苦しい空気感が伝わってくるいい本だった。ただ、この本の冒頭に「本書は学術書ではない」と書かれているようにあくまで回想記でありそれ以上でもそれ以下でもなく、読み物としておもしろかったという感想かな。政治色もちらほらありつつも深入りしすぎない感じがバランスがよく、ベストセラーになったように思った。
教養としての「金利」(田淵直也著)

「金利のある世界」というワードを目にするようになって久しいが、金利について知ろうと思って改めて読んだ一冊。もちろん、知ってることも多かったけど知識として抜けていた部分を補って横断的に知ることができた。金利は景気のバロメーターであって、中央銀行が株価ではなく金利の動向を注視している理由もよくわかったし、無担保コール翌日物やターム物のように名前として目にするものが実際にどうやって運用されているのかなど、より具体的な話を知ることができたのがよかった。
新卒で入った会社で金融系のシステムに携わった時に、上司がこれを読んでおいてくれと言って『スワップ取引のすべて』という本をくれた。この本で金利や現在価値、キャッシュフローの考え方を学んだけどこの本を読んだころはまだ LIBOR が神の金利のような扱いだったな~と思った。

中央銀行が短期金利という一つのパラメータを調整することで経済全体の金融を調整しようとしているのは興味深いと思っている。これはどうでもいいが、Youtube で「レバニキ」という人が作っている FOMC 会見のパロディ吹き替えがおもしろい。FOMC のあとに動画が投稿されるのを待ちわびている…。
『正しい家計管理』&『正しい家計管理・長期プラン編』

これまで我流で家計管理をしてきたが一回くらい本を読んで参考にしてみるかと思って読んでみた本。本当は一年ちょっと前に読んでいて実際に将来のキャッシュフローを作ったりしたけど、年初に改めて読み直してみた。
確かに言ってることは的を射ている部分が多いのだが、書かれていることに少し古くささを感じる。この本は 2010 年代後半に書かれた本だから別に古くないけど、ちらほらでてくる著者の考え方(姿勢?)がなんとなく古く感じてしまう。家計簿を手で書けとか、クレジットカードはなるべく使うな、目的別に口座を分けろ、住宅ローンは早めに返せみたいなところ。投資に対してのスタンスも古さを感じる。
とはいえ正しいと思えることも多いし、どこが古いと感じるのだろう、この違和感はどこからくるのだろうと疑問に思っていた。
--
この記事を書きながらすこしずつ見えてきたのは、この違和感は単に著者が自分でやってきたことを全部肯定しているにすぎなかった、という点だ。ノウハウや考え方を紹介したあとに著者の体験談をはさむことで正当化しているが、「別にそれってこの時代に正当化する理由にならないよね…?」と思ってしまう。著者がキャリアや子育てをした1980年代-2000年代の日本をとりまく環境において正当化された考え方でしょ、って。そして、それについては特に断りが書かれているわけでもない。
家計簿の付け方、資産を列挙しておくなどの紹介されるメソッド自体はそれなりに普遍的なもので今後も役に立つものだと思った。ただし、述べられている筆者の家計に対する考え方が今後も正しいかはけっこう疑問点である。とはいえ、家計管理をしてこなかった人に対して、多くの選択肢を述べるのも分かりづらいからな。自分はもう15年以上は家計簿つけていて、それなりにやってるから単に対象読者じゃなかったということだったのだろう。
ちょっと批判的になっちゃったけど、改めて家計簿の付け方、キャッシュフロー表の作り方などのメソッド自体はとても参考になった、ということだ。
--
このブログは Ghost Pro を使っているのだが、Amazon のリンクを埋め込んでもサムネイルが表示されないのが困る。調べたところもうずいぶん前からこの状態で放置されている様子だった。ブログとして結構致命的なんだけど特に直す気はなさそうである。
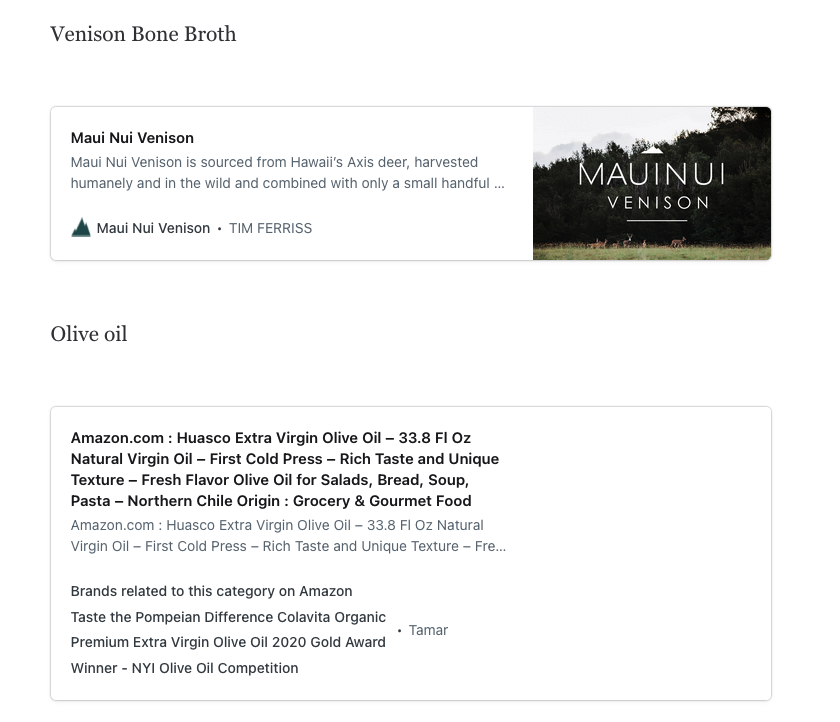
Ghost 自体はオープンソースなので気が向いたら直してみようかな。やらなさそうだけど。





